こんにちは、管理人の胡蝶です
美しい花で空間を彩ってくれた胡蝶蘭ですが、その花が終わりを迎えると、胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかと戸惑ってしまう方は少なくありません。
しかし、適切な手入れをすることで、胡蝶蘭は再び美しい花を咲かせ、長く楽しむことができるのです。
この記事では、胡蝶蘭の花が終わった後の育て方について、二度咲きを目指すための剪定方法から、来年に向けて株を健康に保つための植え替え、適切な水やりや肥料の与え方、さらには根腐れを防ぐための温度管理まで、あらゆる疑問にお答えします。
花茎のどこを切れば良いのか、株の状態の見極め方など、具体的な手順を分かりやすく解説していきますので、初めての方でも安心して挑戦できるでしょう。
大切な胡蝶蘭を来年も、そしてその先も楽しむための知識を身につけていきましょう。
◆このサイトでわかる事◆
- 胡蝶蘭の花が終わった直後にすべきこと
- 二度咲きを成功させるための剪定のコツ
- 来年に向けて株を休ませるお手入れ方法
- 花後の正しい水やりと肥料の管理方法
- 根腐れを防ぐための植え替えのタイミングと手順
- 季節ごとの適切な温度と置き場所の管理
- 病気や害虫から大切な胡蝶蘭を守る方法
| 【PR】【お祝い選びに、もう迷わない!金賞受賞の胡蝶蘭で最高の想いを届ける】 大切な方への開店祝いや昇進祝い、記念日の贈り物。 ありきたりなギフトでは、あなたの「おめでとう」の気持ちは伝わりきらないかもしれません。「らんのお花屋さん・クマサキ洋ラン農園」は、数々の賞を受賞した専門農園です。 ハウスから直送される新鮮で高品質な胡蝶蘭は、その美しさと花持ちの良さが自慢。 法人様向けの豪華な5本立てから、個人のお祝いに最適な可憐な一鉢まで、ご用途に合わせて選べます。ラッピング、メッセージカードなど7つの無料サービスも充実。 7つの無料サービス ・ラッピング ・メッセージカード ・写真送付サービス ・育て方パンフレット ・鉢受けトレイ ・霧吹きスプレー ・品質保証書 特別な日の贈り物は、専門店の胡蝶蘭で、あなたの真心を最高のかたちで届けませんか? |
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、基本のお手入れ方法

◆この章のポイント◆
- まずは花がらを摘み取り株の体力を温存
- 二度咲きを目指す花茎の剪定方法とは
- 来年も楽しむために株を休ませる選択肢
- 花が終わった後の適切な水やりの頻度
- 根腐れを防ぐための管理と見分け方
まずは花がらを摘み取り株の体力を温存
胡蝶蘭の豪華な花が一つ、また一つとしおれていく様子は少し寂しいものですが、ここからが来シーズンに向けた大切なお手入れのスタートです。
すべての花が咲き終わったら、最初に行うべきことは「花がら摘み」です。
咲き終わった花をそのままにしておくと、植物は種子を作ろうとして、そこに栄養と体力を集中させてしまいます。
これは株全体を弱らせてしまう原因となり、次の開花へのエネルギーを蓄える妨げになるのです。
そのため、胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかと迷ったときは、まずしおれた花を一つずつ丁寧に取り除くことから始めましょう。
花がらは、花茎から手で簡単に取れることが多いですが、取れにくい場合は清潔なハサミを使って、花の付け根の部分からカットしてください。
このとき、まだ緑色で生き生きとしている花茎自体を傷つけないように注意が必要です。
この一手間が、株の体力を温存し、次の二度咲きや来年の開花に向けたエネルギーを蓄えるための重要な第一歩となります。
すべての花がらを摘み取ったら、株全体を観察してみましょう。
葉の色つやは良いか、根は健康かなどをチェックする良い機会です。
この観察を通じて、今後の剪定や植え替えの方針を決めていくことになります。
花がらを摘むという作業は、単なる後始末ではなく、胡蝶蘭と長く付き合っていくためのコミュニケーションの始まりと捉えることができるでしょう。
株への負担を最小限に抑え、次の美しい花へと繋げるために、丁寧な作業を心がけましょう。
咲き終わった花を放置することは、株の体力を無駄に消耗させるだけです。
速やかに花がらを摘み取ることで、その分のエネルギーを葉や根の成長、そして次の花芽の形成へと回すことができるようになります。
この地道な作業こそが、胡蝶蘭を毎年楽しむための基本中の基本と言えるでしょう。
二度咲きを目指す花茎の剪定方法とは
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかという疑問を持つ多くの人が、最も関心を寄せるのが「二度咲き」ではないでしょうか。
一度花が終わった後、同じ花茎から再び花を咲かせる二度咲きは、胡蝶蘭の生命力の強さを感じられる嬉しいイベントです。
この二度咲きを成功させる鍵を握るのが、花茎の「剪定」です。
適切な位置で剪定を行うことで、花茎に残っている成長点を刺激し、新たな花芽の発生を促すことができます。
剪定のタイミングと株の状態の確認
剪定を行う前に、まずは胡蝶蘭の株の状態を確認することが非常に重要です。
二度咲きには相応の体力が必要なため、株が元気であることが大前提となります。
以下の条件を満たしているかチェックしましょう。
- 葉が3枚以上あり、ハリとツヤがある
- 根が白っぽく、または緑色で生き生きしている
- 病気や害虫の被害が見られない
もし葉が黄色くなっていたり、根が黒ずんで腐っていたりするなど、株が弱っている様子が見られる場合は、二度咲きを目指すのは避けた方が賢明です。
その場合は、後述する「株を休ませる選択肢」を選び、まずは株の回復を優先させましょう。
剪定の位置と方法
株が元気であることを確認できたら、いよいよ剪定です。
使用するハサミは、病気の感染を防ぐために必ず火で炙るか、アルコールで消毒してから使いましょう。
剪定する位置は、花茎の根元から節を数え、下から2〜3節目の約1.5cm〜2cm上が基本です。
花茎の節には、新しい花芽や気根になる可能性がある「成長点」が隠れています。
節の少し上で切ることで、この成長点が刺激され、新しい花芽が伸びやすくなるのです。
切る際は、思い切って一気にスパッと切ることが大切です。
これにより、切り口がきれいになり、病原菌が侵入するリスクを減らすことができます。
もし花茎が複数本ある場合は、すべての茎を同じように剪定しても構いませんが、株の体力を考慮して、元気の良い茎を1〜2本だけ残して剪定し、残りは根元から切って株を休ませるという方法もあります。
剪定後は、切り口を自然に乾燥させます。
特別な薬剤などを塗る必要は基本的にありません。
その後は、直射日光の当たらない明るい場所に置き、適切な水やりを続けながら新しい芽が出てくるのを待ちます。
うまくいけば、1ヶ月ほどで新しい花芽が伸び始め、数ヶ月後には再び美しい花を楽しむことができるでしょう。
二度咲きの花は、最初の花に比べると少し小ぶりで、花の数も少なくなる傾向がありますが、それでも再び開花してくれた喜びは格別です。
来年も楽しむために株を休ませる選択肢
二度咲きは非常に魅力的ですが、胡蝶蘭とより長く付き合っていくためには、あえて二度咲きをさせずに「株を休ませる」という選択も非常に重要です。
特に、贈答品として立派に咲き誇っていた胡蝶蘭は、生産者の元で最大限のエネルギーを使って開花しているため、花が終わる頃には体力を消耗しきっているケースが少なくありません。
このような状態で無理に二度咲きを目指すと、株がさらに弱ってしまい、最悪の場合、枯れてしまうこともあります。
そこで、胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかと考えたとき、来年、より大きく立派な花を咲かせるために、今年は株の回復と成長に専念させるという長期的な視点を持つことが大切になります。
株を休ませるための剪定方法
株を休ませる場合の剪定は、二度咲きを目指す場合とは位置が異なります。
花が終わった花茎を、根元の付け根から2〜3cmほど残してバッサリと切り落とします。
このときも、ハサミは必ず清潔なものを使用してください。
花茎を根元から切り取ることで、花を咲かせるために使われていたエネルギーが、すべて葉や根の成長へと向けられるようになります。
これにより、株は失った体力を回復し、次のシーズンに向けて栄養をたっぷりと蓄えることができるのです。
株を休ませるメリット
この方法の最大のメリットは、株が充実することです。
体力が回復し、新しい葉や根が元気に育てば、翌年の花芽の付きも良くなります。
結果として、二度咲きで咲く花よりも、大きく、数も多い、見ごたえのある花を咲かせてくれる可能性が高まります。
また、株が健康になることで、病気や害虫に対する抵抗力も強まるという利点もあります。
剪定後の管理は、基本的に二度咲きを目指す場合と大きくは変わりません。
レースのカーテン越しの柔らかな光が当たるような場所に置き、植え込み材の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。
春から秋にかけての生育期には、規定の倍率に薄めた液体肥料を2週間に1回程度与えることで、株の成長をさらにサポートすることができます。
胡蝶蘭を消耗品として一度きりで終わらせるのではなく、大切なパートナーとして来年も再来年も楽しみたいと考えるのであれば、この「株を休ませる」という選択肢は非常に賢明な判断と言えるでしょう。
花が終わった後の適切な水やりの頻度
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかという管理方法の中で、剪定と並んで重要なのが「水やり」です。
花が咲いている間と同じような感覚で水やりを続けてしまうと、根腐れの原因となり、株を弱らせてしまいます。
花が終わった後の胡蝶蘭は、成長が緩やかになるため、水の吸収量も減少します。
そのため、水やりの頻度を適切に調整することが、株を健康に保つための鍵となります。
水やりの基本原則「乾いたら、たっぷりと」
胡蝶蘭の水やりの基本は、季節や花の有無にかかわらず「植え込み材が完全に乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。
この「乾いたら」というタイミングを見極めるのが最も重要です。
植え込み材としてよく使われる水苔の場合、表面が乾いていても、内部はまだ湿っていることがよくあります。
指を少し差し込んでみたり、鉢を持ち上げて重さを確認したりして、中の芯まで乾いていることを確認してから水やりを行いましょう。
「毎日少しずつ」という与え方は、常に根が湿った状態になり、根腐れを引き起こす最大の原因となるため、絶対に避けてください。
季節ごとの水やり頻度の目安
花が終わった後の水やり頻度は、季節によって大きく変わります。
- 春・秋(生育期):気候が安定し、胡蝶蘭が成長しやすい時期です。植え込み材の乾きも早くなるため、7日〜10日に1回程度が目安となります。
- 夏(成長期):気温が高く、水の蒸発も早いため、5日〜7日に1回程度と、水やりの頻度は最も高くなります。ただし、高温多湿による蒸れには注意が必要です。風通しの良い場所に置き、夕方以降の涼しい時間帯に水やりをするのがおすすめです。
- 冬(休眠期):気温が低くなり、胡蝶蘭の成長はほとんど止まります。水の吸収も非常に少なくなるため、水やりの頻度をぐっと減らす必要があります。1ヶ月に1回程度でも十分な場合があります。植え込み材が完全に乾いてから、さらに数日待つくらいの感覚で水を与えましょう。冬場の水のやりすぎは、根腐れに直結するので特に注意してください。
これらの頻度はあくまで目安です。
お部屋の環境(日当たり、風通し、湿度)によって乾き具合は大きく異なるため、必ず自分の目で見て、手で触って、植え込み材の状態を確認する習慣をつけましょう。
与える水は、常温の水道水で問題ありません。
受け皿に溜まった水は、根腐れの原因になるため、必ず毎回捨ててください。
適切な水やりをマスターすることが、胡蝶蘭を長く元気に育てるための最も重要なスキルの一つと言えるでしょう。
根腐れを防ぐための管理と見分け方
胡蝶蘭の栽培で最も多い失敗例の一つが「根腐れ」です。
特に、胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかと試行錯誤している中で、水のやりすぎによって根腐れを引き起こしてしまうケースは後を絶ちません。
根は植物の生命線を支える非常に重要な器官であり、根が傷んでしまうと、水分や栄養を吸収できなくなり、株全体が弱ってしまいます。
根腐れを防ぐための管理方法と、万が一根腐れしてしまった場合の見分け方を知っておくことは、胡蝶蘭を健康に育てる上で不可欠です。
根腐れの原因
根腐れの最大の原因は、前述の通り「水のやりすぎ」です。
胡蝶蘭の根は、もともと樹木に着生して生活しているため、常に湿った状態を嫌い、乾燥と湿潤のメリハリを好みます。
植え込み材が常にジメジメと湿っていると、根が呼吸できなくなり、酸素不足に陥ります。
この状態が続くと、根の細胞が壊死し、そこから病原菌が侵入して腐敗が進行してしまうのです。
また、鉢の通気性が悪いことや、受け皿に溜まった水をそのままにしておくことも、根腐れを助長する大きな要因となります。
根腐れのサインと見分け方
根腐れは、土の中で静かに進行するため、初期段階では気づきにくいことが多いです。
しかし、注意深く観察すれば、いくつかのサインを見つけることができます。
- 葉の異変:葉にハリがなくなり、シワシワになる。黄色く変色して落ちてしまう。これは、根が水分をうまく吸収できていないサインです。
- 植え込み材の異変:表面にカビが生えたり、常に湿っていて乾きにくくなったりします。
- 根の状態:最も確実な確認方法です。鉢が透明なビニールポットの場合は、外からでも根の状態を確認できます。健康な根は、白っぽく太い、または先端が緑色をしています。一方、根腐れした根は、黒や茶色に変色し、触るとブヨブヨと柔らかく、スカスカになっています。
これらのサインが見られた場合は、迷わず植え替えを行い、根の状態を直接確認する必要があります。
根腐れを防ぐための管理
根腐れを防ぐための基本は、以下の3点です。
- 適切な水やり:植え込み材が完全に乾いてから、たっぷりと与える。このメリハリが最も重要です。
- 通気性の確保:素焼き鉢や、スリットの入った鉢など、通気性の良い鉢を選ぶことが推奨されます。また、風通しの良い場所に置くことも大切です。
- 受け皿の水を捨てる:水やり後に受け皿に溜まった水は、根が常に水に浸かる原因になるため、必ず捨てる習慣をつけましょう。
これらの基本的な管理を徹底するだけで、根腐れのリスクは大幅に減少します。
胡蝶蘭の健康は、目に見えない根の状態にかかっていることを常に意識し、丁寧な管理を心がけましょう。
もし根腐れを発見した場合は、次の章で解説する「植え替え」を行い、腐った根をすべて取り除いて再生を図ります。
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、長期的な育て方のコツ
◆この章のポイント◆
- 植え替えのタイミングと手順を解説
- 生育期に与える肥料の適切な使い方
- 季節ごとの適切な温度管理のポイント
- 病気や害虫から胡蝶蘭を守るには
- 来年も美しい花を咲かせるための準備
植え替えのタイミングと手順を解説
胡蝶蘭を長期間にわたって健康に育て、毎年花を楽しむためには、「植え替え」が欠かせない作業となります。
植え替えは、根が伸びるスペースを確保するだけでなく、古い植え込み材を新しくすることで、根腐れを防ぎ、良好な生育環境を維持する目的があります。
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかという次のステップとして、植え替えは株の健康をリフレッシュさせる重要なメンテナンスです。
植え替えの最適なタイミング
植え替えに最適な時期は、胡蝶蘭が最も元気に成長を始める4月〜6月頃の春先です。
この時期は、気温が安定しており、植え替えによる株へのダメージからの回復が早くなります。
花が終わった直後や、寒い冬の時期に植え替えを行うと、株が弱ってしまい、回復が遅れることがあるため避けるのが賢明です。
植え替えの頻度は、2年に1回が目安です。
ただし、以下のようなサインが見られた場合は、2年を待たずに植え替えを検討しましょう。
- 鉢底から根がたくさん飛び出している
- 水苔やバークなどの植え込み材が古くなり、黒ずんだり異臭がしたりする
- 根腐れの兆候が見られる
植え替えの手順
植え替えは、胡蝶蘭にとって大手術のようなものです。
手順をしっかりと理解し、丁寧に行いましょう。
- 準備するもの:一回り大きな鉢(素焼き鉢がおすすめ)、新しい植え込み材(水苔またはバーク)、清潔なハサミ、ピンセット
- 株を取り出す:鉢の縁を軽く叩きながら、胡蝶蘭の株をゆっくりと引き抜きます。根が鉢に張り付いている場合は、無理に引っ張らず、鉢を割って取り出すことも検討します。
- 古い植え込み材を取り除く:根に絡みついた古い水苔やバークを、ピンセットなどを使って優しく丁寧に取り除きます。このとき、健康な根を傷つけないように細心の注意を払いましょう。
- 傷んだ根を整理する:黒や茶色に変色して腐った根、スカスカになった古い根を、消毒したハサミで切り取ります。白っぽくハリのある健康な根は絶対に切らないでください。
- 新しい鉢に植え付ける:新しい鉢の底に発泡スチロールなどを少し入れて通気性を確保し、株を中央に置きます。根の周りに、新しい植え込み材を隙間なく、しかし固すぎないように詰めていきます。水苔の場合は、事前に水で戻し、固く絞ってから使います。
植え替え後の管理
植え替え直後の胡蝶蘭は、ダメージを受けて非常にデリケートな状態です。
植え付け後、すぐには水を与えず、1週間〜10日ほどはレースのカーテン越しの明るい日陰で休ませます(これを「養生」と呼びます)。
これにより、根の切り口が乾き、そこからの病原菌の侵入を防ぎます。
最初の水やりは、養生期間が終わってから行い、その後は通常の水やりサイクルに戻します。
また、植え替え後1ヶ月ほどは肥料を与えないようにしましょう。
適切な植え替えを行うことで、胡蝶蘭は再び元気に根を張り、次の美しい花を咲かせるための準備を始めることができます。
生育期に与える肥料の適切な使い方
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、次のステップとして株を充実させるためには、適切な「肥料」の管理が重要になります。
花を咲かせるためには多くのエネルギーを必要とするため、花が終わった後の株は栄養不足の状態にあることが少なくありません。
特に、春から秋にかけての「生育期」には、新しい葉や根を成長させるために、外部から栄養を補給してあげることが、来年の開花に繋がります。
肥料を与える時期と与えない時期
肥料は、胡蝶蘭が成長している「生育期」にのみ与えるのが原則です。
具体的には、最低気温が18℃を上回るようになる5月頃から、涼しくなり始める9月頃までが肥料を与える適切な期間です。
逆に、気温が低くなり成長が緩慢になる冬場(休眠期)や、真夏の厳しい暑さで株が夏バテしている時期には、肥料を与えるのを止めます。
成長していない時期に肥料を与えると、吸収されなかった肥料分が根を傷め、「肥料焼け」という根腐れに似た症状を引き起こす原因になるため注意が必要です。
また、植え替え直後の1ヶ月間も、根がデリケートな状態なので肥料は与えません。
肥料の種類と与え方
胡蝶蘭に適した肥料は、園芸店などで手に入る洋ラン用の液体肥料です。
液体肥料は効果が早く、濃度の調整がしやすいのが特徴です。
与え方のポイントは「薄く、長く」です。
肥料のパッケージに記載されている規定の希釈倍率よりも、さらに薄めの2000倍〜3000倍程度に薄めたものを、10日〜2週間に1回、水やりの代わりに与えるのが安全で効果的です。
「早く大きくしたい」という気持ちから濃い肥料を与えたり、頻繁に与えたりすると、かえって根を傷つけて株を弱らせてしまうため、絶対にやめましょう。
固形の置き肥(おきごえ)を使用する方法もありますが、効果がゆっくりで、肥料の効き具合が分かりにくいため、初心者の方はまず液体肥料から始めることをお勧めします。
適切な時期に、適切な濃度の肥料を正しく与えることで、胡蝶蘭は体力を回復し、つややかな葉を茂らせ、太く健康な根を伸ばしていきます。
この生育期の充実度合いが、来シーズンにどれだけ美しい花を咲かせられるかを左右すると言っても過言ではありません。
季節ごとの適切な温度管理のポイント
胡蝶蘭は熱帯地方原産の植物であるため、日本の四季の変化、特に夏の暑さや冬の寒さは大きなストレスとなります。
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかと考える上で、長期的に株を健康に保つためには、季節に合わせた「温度管理」が非常に重要です。
適切な温度環境を整えることが、生育を促し、病気を予防し、そして来年の花芽形成へと繋がっていきます。
胡蝶蘭が好む温度
胡蝶蘭が最も快適に過ごせる温度帯は、18℃〜28℃程度です。
人間が快適だと感じる室温とほぼ同じなので、基本的には室内で管理するのが最も育てやすいと言えるでしょう。
この温度帯を基準に、季節ごとの対策を考えていきます。
季節別の管理ポイント
春(4月〜6月)
春は、胡蝶蘭にとって最も過ごしやすい季節です。気温が安定し、生育が旺盛になります。日中は窓際のレースのカーテン越しなど、明るく風通しの良い場所に置いてあげましょう。夜間の冷え込みが15℃を下回るようなら、窓際から部屋の中央へ移動させると安心です。
夏(7月〜8月)
日本の夏は、胡蝶蘭にとっては過酷な季節です。特に30℃を超えるような猛暑は、株を弱らせる「夏バテ」の原因になります。直射日光は葉焼けを起こすため絶対に避け、遮光ネットやすだれを活用して、50%〜70%程度の遮光を心がけます。エアコンの風が直接当たらない、風通しの良い涼しい場所で管理することが重要です。高温多湿による蒸れは病気の原因になるため、サーキュレーターなどで空気を循環させるのも効果的です。
秋(9月〜10月)
残暑が和らぎ、過ごしやすい気候に戻ります。春と同様に管理しますが、秋は来年の花芽を形成させるための重要な時期でもあります。朝晩の気温が下がり始め、昼夜の温度差が出てくることで、花芽の分化が促進されます。台風などで急に気温が下がる日もあるため、天気予報をこまめにチェックしましょう。
冬(11月〜3月)
冬の寒さは胡蝶蘭にとって最も危険です。最低でも10℃以上、できれば15℃以上を保てる環境が必要です。気温が10℃を下回ると、株が凍傷になったり、成長が完全に止まって枯れてしまったりする可能性があります。日中は日当たりの良い窓際に置き、夜間は窓からの冷気が直接当たらないように、部屋の中央に移動させたり、段ボール箱で囲ったりするなどの防寒対策をしましょう。暖房器具の温風が直接当たる場所も乾燥しすぎるため避けてください。
このように、一年を通して適切な温度管理を行うことが、胡蝶蘭の健康維持の基本です。
人間が過ごしやすい環境を意識してあげることが、成功への近道と言えるでしょう。
病気や害虫から胡蝶蘭を守るには
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、適切な手入れを続けていても、時には病気にかかったり、害虫の被害に遭ったりすることがあります。
早期発見・早期対処が、被害を最小限に食い止め、大切な株を守るためには不可欠です。
日頃から胡蝶蘭の様子をよく観察し、異常にいち早く気づけるようにしておきましょう。
注意すべき主な病気
胡蝶蘭がかかりやすい病気の多くは、カビ(糸状菌)や細菌が原因で、高温多湿の環境で発生しやすくなります。
- 軟腐病(なんぷびょう):細菌が原因で発生。葉に淡い褐色のシミができ、水が滲んだようになり、次第に腐って悪臭を放ちます。進行が非常に早く、発見が遅れると手遅れになることが多い危険な病気です。
- 炭疽病(たんそびょう):カビが原因。葉に黒くくぼんだ斑点が現れ、徐々に広がっていきます。
- 根腐れ:前述の通り、水のやりすぎや通気性の悪さが原因で根が腐る状態です。これも病気の一種と捉えることができます。
これらの病気を発見した場合、まずは病気にかかった部分を、周囲の健康な組織も含めて大きめに切り取ります。
使用するハサミは必ず消毒し、他の株への感染を防ぎましょう。
切り取った後は、専用の殺菌剤を散布して様子を見ます。
軟腐病の場合は特に感染力が強いため、他の植物から隔離して管理することが重要です。
予防策としては、風通しの良い場所に置き、葉に水がかかったら拭き取るなど、多湿な環境を作らないことが最も効果的です。
注意すべき主な害虫
害虫は、植物の汁を吸って株を弱らせたり、ウイルスを媒介したりします。
- カイガラムシ:葉の付け根や裏側に、白や茶色の殻をかぶった小さな虫が付着します。ベタベタした排泄物(すす病の原因になる)を出すのが特徴です。
- ハダニ:非常に小さく肉眼では見えにくいですが、葉の裏に寄生し、葉の養分を吸います。被害が進むと、葉にかすり状の白い斑点が現れ、元気がなくなります。乾燥した環境で発生しやすいです。
- アブラムシ:新芽や蕾など、柔らかい部分に群がって汁を吸います。
害虫を発見したら、数が少ないうちは歯ブラシやティッシュなどでこすり落とすのが確実です。
ハダニは水に弱いため、定期的に葉の裏に霧吹きで水をかける「葉水(はみず)」が有効な予防策になります。
大量に発生してしまった場合は、専用の殺虫剤を使用して駆除します。
病害虫の予防は、日々の観察から始まります。
水やりの際に葉の裏や付け根をチェックする習慣をつけることで、異変の早期発見に繋がり、胡蝶蘭を長く健康に保つことができるでしょう。
来年も美しい花を咲かせるための準備
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、その最終目標は、やはり「来年も美しい花を咲かせる」ことでしょう。
これまでの剪定、植え替え、水やり、肥料、温度管理といった一連のお手入れは、すべてこの目標のために繋がっています。
そして、開花に向けた最後の仕上げとして、花芽をつけさせるための「花芽分化(はなめぶんか)」というプロセスが重要になります。
花芽分化のメカニズム
胡蝶蘭は、単に株が成熟しただけでは花芽をつけません。
花芽を形成するためには、一定期間、低温の環境にさらされるというスイッチが必要になります。
具体的には、夜間の最低気温が18℃以下になる環境に、3週間〜1ヶ月ほど置くことで、葉の成長から花の成長へと切り替わり、花芽が形成されるのです。
このプロセスを「花芽分化誘導」と呼びます。
花芽をつけさせるための具体的な管理
花芽分化を促すのに最適な時期は、夏の暑さが和らぎ、涼しくなってくる秋(9月下旬〜11月頃)です。
この時期に、胡蝶蘭を屋外やベランダ、または暖房の入っていない涼しい部屋に置き、自然の涼しさに当ててあげます。
ただし、急激な温度変化は株にストレスを与えるため、徐々に慣らしていくことが大切です。
また、霜が降りるような寒さは厳禁なので、天気予報には注意しましょう。
この時期、水やりは控えめにし、肥料は与えないようにします。
株に少しストレスを与えることで、子孫を残そうとする本能が刺激され、花芽がつきやすくなるとも言われています。
無事に花芽分化が成功すると、葉の付け根あたりから、根とは少し違う、先端が尖った緑色の芽が顔を出します。
これが花芽です。
花芽が出てきたら、再び暖かいリビングなどに取り込み、通常の管理に戻します。
花芽は光に向かって伸びる性質があるので、鉢の向きをくるくる変えず、一定の方向から光が当たるようにすると、花茎がまっすぐきれいに伸びます。
花芽が伸びてきたら、倒れないように支柱を立てて誘引してあげましょう。
花芽が出てから開花するまでには、3〜4ヶ月ほどかかります。
日々の成長を観察しながら、春の開花を心待ちにする時間は、ガーデニングの醍醐味の一つと言えるでしょう。
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、長く楽しむ秘訣
ここまで、胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいかという疑問に答えるべく、具体的なお手入れ方法を解説してきました。
豪華で繊細な見た目から、育てるのが難しいと思われがちな胡蝶蘭ですが、その生態と基本的な育て方のポイントさえ押さえれば、何年にもわたって美しい花を咲かせてくれる、非常に生命力の強い植物です。
最後に、胡蝶蘭と長く付き合っていくための秘訣をまとめます。
胡蝶蘭の管理で最も大切なのは、「過保護にしすぎない」ことかもしれません。
特に水やりは、可愛さのあまりつい頻繁にあげたくなりますが、それが根腐れという最大の失敗に繋がります。
「乾いたら、たっぷりと」という基本原則を徹底し、少し乾かし気味に管理するくらいがちょうど良いのです。
また、二度咲きを急ぐあまり、弱った株に無理をさせるのも禁物です。
時には来年の満開を夢見て、株をじっくり休ませてあげるという長期的な視点を持つことが、結果的に長く楽しむための近道となります。
そして何より大切なのは、日々の観察です。
葉の色つや、根の状態、新しい芽の動きなど、胡蝶蘭が発する小さなサインに気づいてあげること。
それが適切なタイミングでのお手入れに繋がり、病害虫の早期発見にも繋がります。
胡蝶蘭の花が終わったらどうしたらいいか、その答えは一つではありません。
あなたの家の環境や、株の状態によって、最適な管理方法は少しずつ異なります。
この記事で紹介した基本をベースに、あなたの胡蝶蘭と対話しながら、最適な育て方を見つけていってください。
その試行錯誤の過程こそが、植物を育てるという趣味の奥深さであり、再び花が咲いたときの喜びを何倍にも大きくしてくれるでしょう。
本日のまとめ
- 胡蝶蘭の花が終わったらまず花がらを摘む
- 株の体力を温存することが次の開花への第一歩
- 元気な株は二度咲きに挑戦できる
- 二度咲きの剪定は花茎の下から2〜3節の上で行う
- 株が弱っている場合は根元から切り株を休ませる
- 水やりは植え込み材が完全に乾いてからが鉄則
- 水のやりすぎは根腐れの最大の原因
- 植え替えは2年に1回、春先に行うのが最適
- 植え替え時に腐った根はきれいに取り除く
- 肥料は成長期の春から秋にかけて薄めて与える
- 冬場の肥料は根を傷めるので与えない
- 最適な生育温度は18℃から28℃
- 夏の暑さと冬の寒さ対策が重要
- 病害虫は早期発見と風通しの良い環境での予防が大切
- 来年の花芽は秋の涼しさにあてることで付きやすくなる
| 【PR】【お祝い選びに、もう迷わない!金賞受賞の胡蝶蘭で最高の想いを届ける】 大切な方への開店祝いや昇進祝い、記念日の贈り物。 ありきたりなギフトでは、あなたの「おめでとう」の気持ちは伝わりきらないかもしれません。「らんのお花屋さん・クマサキ洋ラン農園」は、数々の賞を受賞した専門農園です。 ハウスから直送される新鮮で高品質な胡蝶蘭は、その美しさと花持ちの良さが自慢。 法人様向けの豪華な5本立てから、個人のお祝いに最適な可憐な一鉢まで、ご用途に合わせて選べます。ラッピング、メッセージカードなど7つの無料サービスも充実。 7つの無料サービス ・ラッピング ・メッセージカード ・写真送付サービス ・育て方パンフレット ・鉢受けトレイ ・霧吹きスプレー ・品質保証書 特別な日の贈り物は、専門店の胡蝶蘭で、あなたの真心を最高のかたちで届けませんか? |
〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●
宮司に就任祝いのマナー完全ガイド|金額相場からのし袋まで解説
落成祝いの相場を徹底解説!贈る相手別の金額からマナーまで
〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●
参考サイト
https://www.hanamonogatari.com/fs/hanamonogatari/c/phalaenopsis-sodatekata-hanago
https://hitohana.tokyo/note/299
https://www.ranya.co.jp/phalaenopsis/after-phalaenopsis-flowers/
https://www.andplants.jp/blogs/magazine/phalaenopsis-aphrodite-after-blooming
https://alon-alon.com/blogs/phalaenopsis-orchid-column/after-blooming-phalaenopsis-orchid

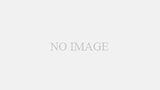

コメント